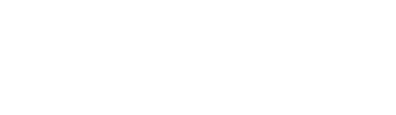小倉城 天守閣
小倉城の歴史

関門海峡に面した小倉は、陸海の交通の要衝として古くから砦や城が築かれ、多くの豪族が争いを繰り広げた歴史が残っています。小倉城の歴史は戦国時代の末期、1569年に中国地方の毛利氏が現在の地に城を築いたことから始まります。その後、高橋鑑種(たかはし あきたね)や毛利勝信(もうり かつのぶ)が居城し、関ヶ原の戦いで功績を挙げた細川忠興(ほそかわ ただおき)が1602年に本格的な築城を開始。完成までに約7年を要しました。
小倉城の都市計画と城下町の発展
細川忠興が築いた小倉城は、城下町全体を城郭とする壮大な都市計画のもとで建設されました。全国で五番目の規模を誇り、西日本では姫路城に匹敵する巨大な城郭でした。特に九州では群を抜く大きさで、熊本城の約2倍の規模を誇りました。
小倉の町は本州と九州を結ぶ玄関口であり、中津街道や長崎街道の起点でもありました。そのため「九州のすべての道は小倉に通じる」とも言われ、活気にあふれていました。城下町では、城の周囲に家臣の武士が住み、その外側には町人が暮らしていました。忠興は城下町の発展を目指し、各地から商人や職人を招き、商工業を保護。さらに外国貿易を奨励し、同時に祇園祭りも誕生させました。
小倉城の変遷と小笠原氏の時代
細川氏が熊本へ転封された後、1632年には細川家と姻戚関係にある播磨国明石の小笠原忠真(おがさわら ただざね)が入国。小倉・小笠原藩は、将軍・徳川家光から九州諸大名の監視という特命を受けていました。この時期、小倉は九州各地へ通じる街道の起点として重要な地位を確立し、小倉城もさらに充実。城下町も発展を続けました。小笠原忠苗(おがさわら ただみつ)の時代には、城内下屋敷に泉水を持つ回遊式庭園も造られました。しかし1837年、城内で発生した火災により全焼。その2年後に再建されましたが、天守閣は再建されませんでした。
小倉城の近代史
幕末になると、小倉は長州藩を攻める拠点となりました。小倉藩と熊本藩は勇敢に戦いましたが、他の九州諸藩の兵には積極的な戦意がなく、ついに1866年、小倉城に自ら火を放ち撤退を余儀なくされました。明治10年の西南戦争では、小倉城に駐屯していた歩兵第14連隊が、乃木希典将軍に率いられて出征。その後、歩兵第12旅団や第12師団の司令部が城内に置かれました。太平洋戦争後は米軍に接収されましたが、1957年に解除。1959年、市民の熱い要望により天守閣が再建されました。
再建された天守閣の特徴
天守閣案内

小倉城の天守閣は天保8年(1837年)の火災で焼失しましたが、市民の熱い要望により、昭和34年(1959年)に再建されました。現在の天守閣は、大阪城・名古屋城に次ぐ国内で三番目の規模を誇ります。
平成31年(2019年)3月には、約30年ぶりに展示内容と内装をリニューアルし、「体験型観光スポット」として生まれ変わりました。
1階から5階まで移動できるエレベーターを新設し、より多くの方に快適にご利用いただけるようになりました。さらに、天守閣の夜間貸切も可能で、特別なイベントやプライベートな集まりにご利用いただけます。
小倉城の貸切についてはこちらをご覧ください
各フロアのご案内
1階:エンターテイメントエリア「小倉城シアター&体験コーナー」
1階は、小倉城の歴史を楽しみながら学べるエンターテイメントエリアです。
俳優・草刈正雄さんのナレーションによる「小倉城シアター」では、小倉城400年の歴史を約10分に凝縮した映像を上映。
さらに、着物や戦国武将の衣装を身にまとって撮影できる「なりきりコーナー」や、馬上から的を射るスリルを体験できる「流鏑馬(やぶさめ)ゲーム」など、大人から子どもまで楽しめる体験型コンテンツが充実しています。
3階:宮本武蔵と佐々木小次郎 - 小倉が舞台の巌流島の戦い
3階では、小倉にゆかりの深い宮本武蔵と佐々木小次郎の生涯を紹介しています。関門海峡に浮かぶ巌流島で繰り広げられた決闘は、小倉藩主・細川忠興のもとで行われた、小倉の物語です。
展示では、佐々木小次郎の愛刀を再現した真剣や、宮本武蔵の木刀(ともにレプリカ)を展示。さらに、巌流島の決闘の名場面を再現した「巌流島フォトスポット」では、佐々木小次郎になりきり、頭上から切りかかる宮本武蔵のリアルフィギュアとともに記念撮影ができます。
また、巌流島の戦いや宮本武蔵の生涯を描いた映像も必見。剣豪としての武蔵だけでなく、晩年に芸術家としても活躍した一面も紹介しており、宮本武蔵ファンにはたまらない展示となっています。
5階:展望スペース&カフェ・バー - 天守閣で特別なひとときを
5階の展望スペースからは、小倉の街並みを一望できます。さらに、全国で唯一、天守閣最上階で飲食を楽しめるカフェ・バーを併設。日中はカフェとして利用でき、土曜の夜にはお酒を楽しめる「ナイトキャッスル」など、特別なひとときを過ごせるイベントも開催されています。
キャッスルカフェについては「こちら」をご覧ください。
小倉城内散策
城内の門跡(門跡めぐり)