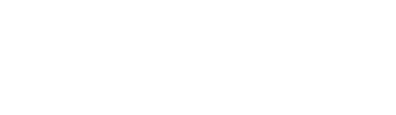「香道」は、室町時代から続く日本の伝統文化のひとつです。もともとは奈良時代に供香(くこう)として伝えられましたが、その後、足利義政の時代に小さな香木を炷(た)く「聞き香」が始まりました。「香を聞く」とは、一片の香木が持つ繊細な香りを、心を落ち着けてじっくり鑑賞し、楽しむことを意味します。
香道の席では、いくつかの種類の香木を炷き、その香りの名前を当てる「組香(くみこう)」という競技形式で行われることもあります。香道の主な流派である志野流は、創始者の志野宗信から400年以上にわたって受け継がれてきた、武家社会に根ざした正統な流派です。志野流では、香りを「嗅ぐ」とは言わず、「聞く」と表現し、心を集中して香りを味わうことが大切にされています。特に、武家の作法や精神性を重んじるのが特徴です。
また、香道に使われる香炉や香合などの道具は、美術品としても高い価値があり、茶道や華道と並んで、日本の総合的な美意識を表しています。「香を聞く会」では礼儀作法が重視され、香木の種類を当てる「組香(くみこう)」を通じて、文学や歴史とも結びついた奥深い世界を体験することができます。
開催日時
令和7年11月23日(日)
1席目 9:30-10:40
2席目 11:00-12:10
3席目 12:30-13:40
4席目 14:00-15:10
※各席20名
場所
小倉城庭園 和室
料金
一般:3,500円(高校生以上)
※小倉城庭園への入園料込み
予約
11月4日(火)から受付開始
電話でご予約ください。(小倉城庭園:093-582-2747)